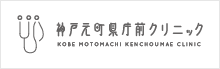糖尿病ノート
7月2017
うどん?そば?それともそうめん?(管理栄養士)
2017.07.11
当院には3名の管理栄養士がおり、いつでも栄養相談を受けて頂くことができます。
今後、ホームページでも糖尿病や生活習慣病の食事療法に関する情報を掲載していきます。
ぜひ、ご参考にして下さい。

いよいよ夏本番。あっさり・さっぱりしたものが食べたくなりますよね。
うどん・そば・そうめん。どのくらいのエネルギーがあるかご存じですか?
| うどん(1玉) | そば(1玉) | そうめん(1束) |
| 210kcal | 211kcal | 343kcal |
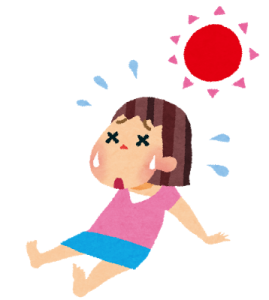
お気づきですか?そうめんって意外にカロリーが高いのです。これは、製造過程で油が使われているから。
それならうどんかそばの方がたくさん食べられる!ではありません。たくさん食べれば、摂取エネルギーは高くなってしまいます。
工夫次第で、バランスのよい食事に変わりますよ!
たとえば、トッピングの選び方です。ついつい天ぷらやお肉を選びがちでは?
お供に稲荷寿司や炊き込みご飯を追加していませんか?
脂質の取り過ぎや糖質の重ね食べは、血糖値を乱してしまいます。
ここで野菜の登場です!
トッピングやもう一品を野菜やきのこ、大豆製品に置き換えてみてはいかがでしょう。「主食だけの食事」が「バランスの取れた食事」に近づくのではないでしょうか。
工夫一つで野菜摂取のチャンスをつかみましょう。
管理栄養士 山本

カテゴリー|